LECのVマジック攻略講座を使って、司法書士試験の勉強を本格的に進めている。
特に今は民法の復習に力を入れているのだけれど、思ったよりも手間取っているのが正直なところだ。
この講座は、1回の配信で3ユニット、それぞれ1時間ずつの講義が収録されている。つまり、1回分で合計3時間。復習の流れとしては、テキストの読み込みから始まり、講義視聴、復習問題、そしてテキスト再確認と、一通りやろうとすると1ユニットでもそこそこ時間がかかる。
これまでは、1日2ユニットから3ユニットの復習が余裕でこなせていた。けれども民法の第2巻、債権編に入ってからは、急にペースが落ちてしまい、1日1ユニットが精一杯になってしまった。
「債権はどこも難しい」という現実
正直なところ、最初は自分の勉強の仕方が悪いのかな、集中力が落ちているのかなと焦りを感じた。
けれども、先生が講義の中でこう言っていた。
「債権はどこも難しい。直前期には債権に時間をかけられない。でも必ず4問出る。だからこそ、今しっかり時間をかけて理解しておこう。」
その言葉にハッとした。そうか、自分だけが遅れているわけじゃないのだ。もともと債権は分量も多く、内容も複雑で、しかも条文の横断的な理解を求められる。だから誰にとってもハードルが高い分野なのだ。
確かに債権に入ってから、今までと比べて一気に「理解してから次に進む」という負荷が重くなった。物権のときはイメージで整理できる部分も多かったけれど、債権は抽象的で、条文を正確に追わないと落とし穴にハマる。だから復習のスピードが落ちるのは当然のことだったのだ。
今だからこそ、理解に時間をかけるべき
試験直前期になると、誰もが「過去問の回転」と「暗記」に集中する。債権のような重たい分野に時間を割く余裕はなくなる。だからこそ、今この段階で、あえて時間をかけて理解しておくことに意味がある。
「まずは理解すること。その後、暗記して自動的にすぐ答えられるようにする」
この先生の言葉が胸に残っている。司法書士試験は、暗記勝負のように見えて、実は「理解を土台にした暗記」でなければ長期的に定着しない。特に債権は事例問題で出題されることも多いので、丸暗記で対応できるほど甘くはない。
そう思うと、今の「1日1ユニットが限界」というペースも、決して無駄ではない。むしろ「債権を理解しきるまで粘る」ことが、後の大きな財産になるのだと自分に言い聞かせている。
勉強の質をどう上げるか
ここで自分なりに工夫していることがある。
- 講義前に必ずテキストをざっと読む
これをしておくと、講義で出てくる話が「初めまして」ではなくなり、頭に入りやすい。 - 復習時は、条文番号を一緒に確認する
債権は条文の世界。条文を飛ばして理解しようとすると、必ず抜け落ちが出る。 - ノートに「自分の言葉でまとめる」
難しい概念こそ、自分の口で説明できるレベルまで落とし込む。曖昧なままだと、本試験の問題文を読んだ瞬間に固まってしまう。 - 「分からない」を恐れない
1回読んで分からないことは当たり前。何度も往復して初めて血肉になる。
これらを繰り返すことで、少しずつ理解の輪郭がはっきりしてきた。スピードは落ちても、確実に力がついている実感はある。
自分に言い聞かせたいこと
「債権は必ず4問出る」
これはプレッシャーであると同時に、努力の方向を示してくれる羅針盤でもある。
直前期にはどうしても「時間が足りない」と焦ってしまうだろう。そのときに「債権は基礎を理解してあるから大丈夫」と自分に言えるかどうか。今の粘り強さが、きっとその支えになる。
試験勉強は長いマラソンだ。時にペースが落ちることもあるけれど、それは失敗ではなく「必要な調整」だと思いたい。
今日のまとめ
- 債権に入ってから復習スピードが落ちたのは自然なこと
- 直前期には債権に時間をかけられないからこそ、今じっくり理解しておく
- 暗記よりもまずは理解。その後に自動化へ
- 「遅い自分」に焦らず、必要な時間をかけることが未来の力になる
これからも焦らず、一歩ずつ。
債権という壁を越えることが、司法書士合格への道を切り開くはずだ。
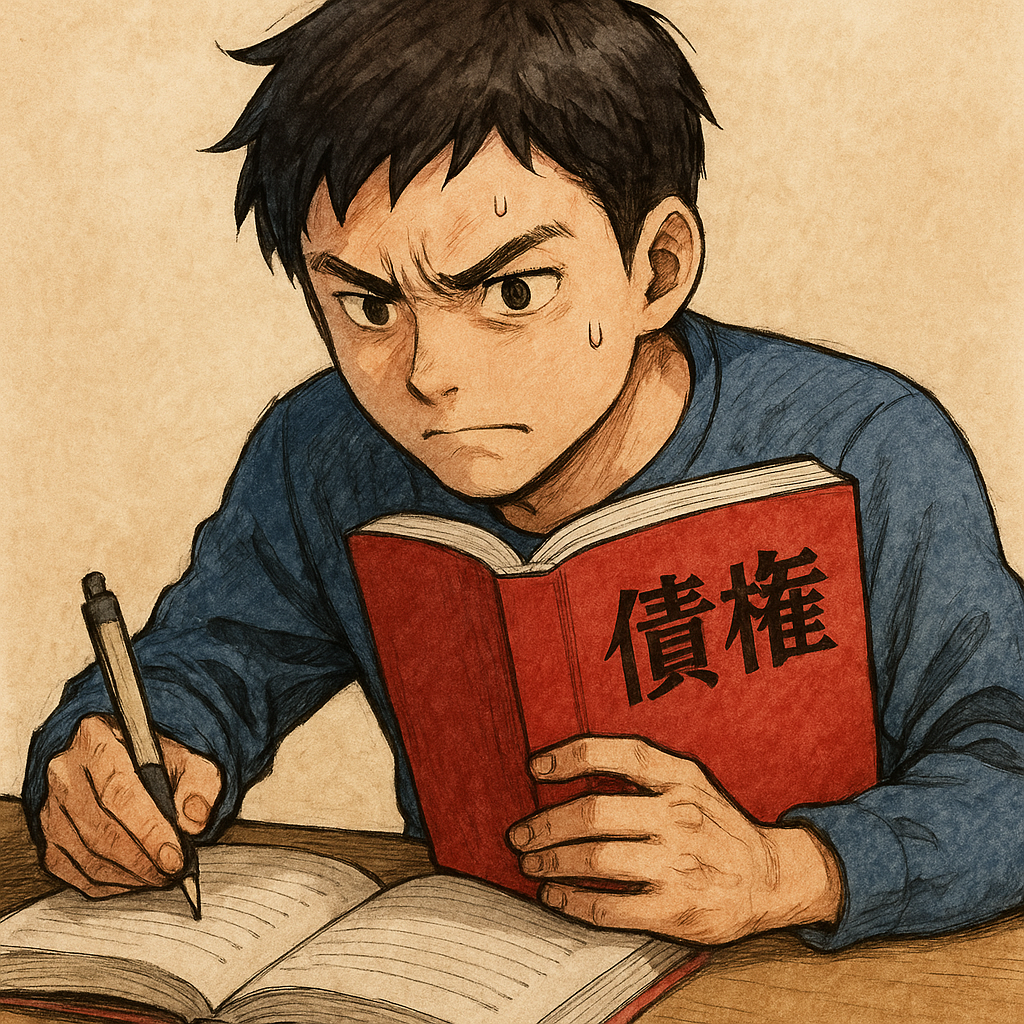


コメント