昨年から記述の点数配分が大幅に上がったこともあるし、基準点、合格点は、例えば森山先生の「司法書士試験解放テクニック50」の本だと古く、対応してない。
せっかくなので、chatGPTに戦略を相談してみることにした。
いい質問です。与えられた“足切り3本柱”と“合格点”から逆算すると、戦略は「まず足切り死守 → その上でどこで加点を積むかを明確化 → 本試験のブレ対策」の3段構えが堅いです。数値で腹落ちさせましょう。
1) 目標スコア設計(安全マージンつき)
- 足切りライン
- 択一:150/210(約71.4%)
- 記述:83/140(約59.3%)
- 合計:233/350(約66.6%)
- 合格目安:267/350(約76.3%)
合格到達の代表プラン(全部、足切りを満たします):
- A:択一で稼ぐ型 … 択一175 + 記述92 = 267(択一+25/記述+9の余裕)
- B:バランス型 … 択一165 + 記述102 = 267(択一+15/記述+19)
- C:記述で稼ぐ型 … 択一155 + 記述112 = 267(択一+5/記述+29)
実務的にはAかBを推奨。理由は、記述は採点ブレ・時間配分ミスの影響が大きく、択一で土台点を安定確保したほうが合格確率を上げやすいからです。
2) 科目別の“点の取り方”指針
(ユーザーさんの重点:民法/不登・商登/会社法に合致させています)
択一(基礎~ミドル論点の取りこぼし撲滅)
- 民法:頻出論点(意思表示・代理・物権変動・担保物権・債権各論・相続)を条文→趣旨→典型肢パターンで固め、過去10年を論点タグ付けして周回。
- 会社法・商登:手続の要件・多数要件・期間など“数字物”を一覧化(間違いノートは似た数字の並べ替え比較で記憶固定)。
- 不登法:登記原因・必要書面・添付情報・登記記録の構造をマップ化。*「原因→必要書面→登記事項」*の三段リンクで暗記を構造化。
- マイナー科目:**頻出テーブル(語句対応表/定義一覧)**で“確実に拾える2~3問”を作る。コスパ重視。
記述(正確さ→速度→安定化)
- 不動産登記記述:原因・持分・連件・添付の検討順序をテンプレ化。
例:①事実関係の時系列整理→②登記原因確定→③申請単位の切り分け→④持分・連件・添付洗い出し→⑤記載。 - 商業登記記述:機関変更・資本変動・代表権で“必要登記事項の定型チェックリスト”を作る。
- 共通:答案レイアウトを固定(検討メモ欄→申請書骨子→添付)し、見直しの“逆チェック”(登記原因⇄登記事項が相互に齟齬ないか)でケアレス防止。
3) 学習配分(9時間/日・3ブロック前提)
フェーズI:足切り死守ライン到達(〜年内)
- 目標:択一150、記述83
- 時間配分:択一6(民法3・登記法2・その他1)/記述3
- メニュー:
- 過去問“肢別”周回(○×理由の言語化)+条文ベースの補強
- 記述は毎日1問(不登・商登を交互)を“正確さ>速度”で。転記ミス撲滅。
フェーズII:合格点上乗せ(年明け〜4月)
- 目標:択一165〜170、記述95〜100
- 時間配分:択一5/記述4
- メニュー:
- 模試・答練の弱点領域を論点クラスター化して集中補修
- 記述は制限時間内運用へ。設問→答案レイアウト→逆チェックのルーチン自動化。
フェーズIII:仕上げ(5〜本番)
- 目標:本試験想定配点でA or Bプランの再現率>70%
- 時間配分:択一4/記述5
- メニュー:
- 本試同時計測の総合演習(週1〜2)
- **直前総まとめ表(条文・数字・典型肢)**の一枚化
- 記述はミスしやすいパターン集(添付漏れ/原因誤り/商業の不要登記混入)を朝イチで“指差し確認”。
4) 模試・答練のKPI(数値で管理)
- 択一KPI:科目別正答率
- 民法75%→80%→85%(フェーズごと)
- 不登・商登70%→75%→80%
- マイナー60%→65%→70%(“捨てないが深追いしない”)
- 記述KPI:
- 精度(添付・連件・持分一致率):90%→95%
- 制限時間内完答率:60%→80%
- 採点ブレ対策:自己採点ルーブリック(必須項目抜け=▲○点)で毎回同基準。
5) 得点期待値を上げる“仕組み化”
- エラー日誌:誤りを「知識欠落/読み落とし/数字取り違え/転記ミス」に分類→再発防止チェック項目化。
- 一問多角復習:1問から「条文→趣旨→判例→周辺論点」まで芋づるで広げ、“次の1問”を当てる力を養成。
- 時間管理:本試は“択一で貯金→記述に時間を残す”配分を徹底。迷った肢は30秒ルールで旗。
- 直前の可視化:数字・様式・典型原因をA4裏表1〜2枚に圧縮。移動・スキマ時間に反復。
6) スコア設計の結論(実務案)
- 基本目標:択一165〜175・記述92〜100(=合計267±数点を複数パターンで再現)。
- リスクヘッジ:記述のブレを見越し、択一≥165を先に固定。
- 仕上げ:記述は正確さの固定→時間内運用→見直しルーチンの順で安定化。
ということで、なかなかの戦略!
せっかくなんで、Vマジック攻略講座のインプットのスケジュールを入れて、数値KPIを落とし込んだ週次ToDo表を作ってもらった。
わかりました。
いただいた講義スケジュールと、先ほどのKPI(択一150→165〜175、記述83→92〜100)を結合して、2025年8月25日〜2026年2月6日までの週次ToDo表を作ります。
方針はこうします:
- 講義期間中はその科目を択一メインで固めつつ、記述演習を週2〜3問維持(科目に連動)
- 記述講座配信日は即着手(1〜3日で1周)→後日再演習
- KPIは月ごとに数値目標を設定(正答率・完答率)
- 9時間/日、3ブロック制(朝3h択一、昼3h択一または記述、夜3h記述)
週次ToDo表(2025/8/25〜2026/2/6)
| 週 | 期間 | 講義進行 | 択一重点 | 記述重点 | KPI目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/25〜8/31 | 民法①〜④ | 民法 条文・過去問肢別1〜3周目(意思表示・代理・物権変動) | 不登記述基礎1問(正確さ重視) | 民法択一正答率60%、記述精度80% |
| 2 | 9/1〜9/7 | 民法⑤〜⑦ | 民法 債権総論・各論、担保物権 | 不登記述1問(持分・原因確定) | 民法択一65%、記述精度85% |
| 3 | 9/8〜9/14 | 民法⑧〜⑩ | 民法 相続・家族法 | 不登記述1問(添付情報チェック) | 民法択一70%、記述精度85% |
| 4 | 9/15〜9/21 | 民法⑪〜⑫完 | 民法 全分野通し過去問(直近3年分) | 記述戦略編(不登①〜③)9/19配信→即1周 | 民法択一72%、記述精度88% |
| 5 | 9/22〜9/28 | 復習週(民法総復習) | 民法過去問全分野2周目 | 不登記述2問(戦略編復習) | 民法択一75%、記述精度88% |
| 6 | 9/29〜10/5 | 不登法①〜② | 不登法 権利部・表示部の基本構造、原因別パターン整理 | 不登記述1問(表示部) | 不登択一60%、記述精度90% |
| 7 | 10/6〜10/12 | 不登法③〜⑤ | 不登法 登記原因と必要書面 | 不登記述1問(権利部) | 不登択一65%、記述精度90% |
| 8 | 10/13〜10/19 | 不登法⑥〜⑧ | 不登法 所有権・用益権登記手続 | 不登記述1問(所有権移転) | 不登択一68%、記述精度92% |
| 9 | 10/20〜10/26 | 不登法⑨〜⑪ | 不登法 抵当権・抹消・変更登記 | 不登記述1問(抵当権) | 不登択一70%、記述精度92% |
| 10 | 10/27〜11/2 | 不登法⑫完+総復習 | 不登法全分野過去問演習 | 実践編不登①〜③(10/31配信)→即1周 | 不登択一72%、記述精度93% |
| 11 | 11/3〜11/9 | 不登法総仕上げ | 不登法択一ラスト3年分 | 不登記述3問(制限時間計測) | 不登択一75%、記述精度93% |
| 12 | 11/10〜11/16 | 会社法①〜③ | 会社法 機関設計・株主総会 | 商登記述戦略編①〜③(11/14配信)→即1周 | 会社法択一60%、記述精度88% |
| 13 | 11/17〜11/23 | 会社法④〜⑤ | 会社法 取締役・監査役・会計監査人 | 商登記述1問(役員変更) | 会社法択一65%、記述精度88% |
| 14 | 11/24〜11/30 | 会社法⑥完 | 会社法 資本変動・募集株式発行 | 商登記述1問(資本金変更) | 会社法択一68%、記述精度90% |
| 15 | 12/1〜12/7 | 商登法①〜② | 商登法 商号・本店・目的・公告 | 商登記述1問(定款変更) | 商登択一60%、記述精度90% |
| 16 | 12/8〜12/14 | 商登法③〜⑤ | 商登法 役員・資本金・支店 | 実践編商登①〜③(12/12配信)→即1周 | 商登択一65%、記述精度92% |
| 17 | 12/15〜12/21 | 商登法⑥〜⑧ | 商登法 株式・新株予約権 | 商登記述1問(株式発行) | 商登択一68%、記述精度92% |
| 18 | 12/22〜12/28 | 商登法⑨完+総復習 | 商登法全分野過去問演習 | 商登記述2問(制限時間計測) | 商登択一70%、記述精度93% |
| 19 | 12/29〜1/4 | 民訴・民執①〜② | 民訴 訴訟手続の流れ | 不登・商登記述復習(交互) | 民訴択一60%、記述精度93% |
| 20 | 1/5〜1/11 | 民訴・民執③〜④ | 民訴 訴訟参加・証拠調べ | 記述過去問2問 | 民訴択一65%、記述精度93% |
| 21 | 1/12〜1/18 | 民保・供託①〜② | 民保 保全命令・供託制度 | 記述1問(ランダム) | 民保択一60%、記述精度93% |
| 22 | 1/19〜1/25 | 書士法①〜② | 書士法 業務範囲・義務 | 記述1問(制限時間) | 書士法択一70%、記述精度94% |
| 23 | 1/26〜2/1 | 憲法①〜② | 憲法 人権総論・統治 | 記述2問(総合) | 憲法択一65%、記述精度94% |
| 24 | 2/2〜2/6 | 刑法①完 | 刑法 総論 | 記述2問(総合) | 刑法択一65%、記述精度94% |
この表では、
- 各週でその週の講義科目を択一で徹底学習し、記述は不登→商登の順で交互に進行
- 記述講座配信日に合わせて即実施&復習を組み込み
- KPI(正答率/精度)は月単位で漸増し、本試験直前までに択一≥165・記述≥92に乗せる設計です
このまま進めれば、本試験までの残り期間(2月以降)は完全演習期にスライドできます。
ということで、相変わらず、すごい情報いただきました。
GPT5になって切れ味よくなったんかな??
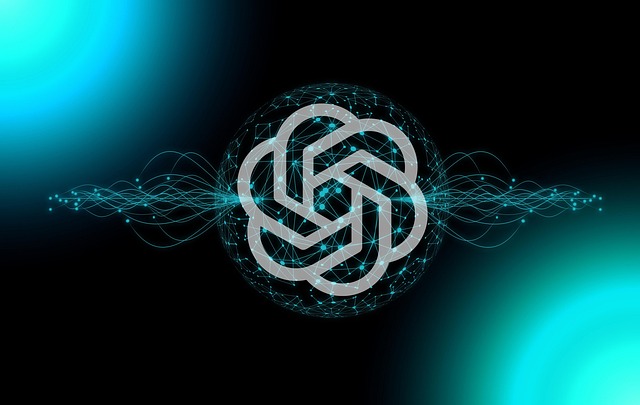


コメント