こんにちは。今日は、司法書士試験の勉強をしている中で感じたことを、少し長めに書いてみたいと思います。
LECの「Vマジック攻略講座」を受講している方ならわかると思うのですが、この講座、週に2回配信されるインプットの授業を中心に進んでいきます。僕もこれまで、その流れに沿って、テキストを読み、講義を受け、復習と問題演習を繰り返してきました。
民法後半に差しかかる中、突如「記述」の波が!
順調に進んでいる…と思ったのもつかの間。民法の後半にさしかかってきたところで、まさかの出来事。
そう、記述の講座が始まってしまったんです。
しかもタイトルは「記述解法習得講座 戦略編」。
「え、ちょっと待って!」と思わず声に出してしまいました。だって、まだ不動産登記法のインプットすら始まっていないんです。いきなり記述の講義が配信されても、頭の中は民法でいっぱいいっぱい。不動産登記法の基礎がなければ解けない問題なんて山ほどあるはず。
正直なところ、「まだ早いよ…」と感じました。
通信講座ならではの「止める勇気」?
もしこれが教室での通学講座だったら、半ば強制的に記述の授業も受けざるを得ません。でも通信は違います。自分のペースで見られる。だからこそ、今までは「ここは一旦止めておこう」と思えば止められたし、「不動産登記法のインプットが終わってから、改めて記述を見ればいいや」と後回しにできました。
僕も最初はそう考えました。「どうせ今見ても理解できない部分が多いんだから、効率的にやろう」と。
でも、その間にさらに「記述」の講座が追加で始まるという現実…。つまり、二重、三重に重なってしまうのです。
逃げてはいけない。覚悟を決める時
そこで気づきました。
もう待っている場合じゃない。
確かに、不動産登記法のインプットがまだ終わっていないのは不安。でも、それ以上に「記述の戦略そのもの」を学ぶ機会を逃すのはもったいない。
だって記述の問題は、知識だけでは突破できません。解法の型や戦略を知っているかどうかで、大きく点数が変わってくるのです。
実際にやってみたら…
半信半疑のまま、記述戦略編の講義を再生してみました。最初は不安でいっぱいでした。「どうせ知識不足でチンプンカンプンになるんじゃないか」と。
ところが、実際に取り組んでみると――意外な発見がありました。
もちろん、不動産登記法の具体的な知識が必要な問題は出てきます。そこは今の自分には歯が立たない。でも、それ以上に問われていたのは、問題文をどう読み取るか、日付や別紙の情報をどう整理するか、そして指示通りに正確に書き出せるかという作業力だったんです。
「なるほど、こういうことか」と思いました。
つまり、知識以前に、まずは“注意深さ”と“情報整理力”が試されている。しかも、そのやり方は講義の中で丁寧に示されていて、「ここはメモを取れ」「ここはチェックを入れろ」と具体的。知識不足で完全には解けなくても、解法の流れを体で覚えていくことができるのです。
先にやっておく価値
やってみて思ったのは、むしろ最初に記述の戦略を学んでおいたほうが良いということです。
知識が揃ってから始めると、「知識はあるのに、書けない」というジレンマに陥りがち。でも、最初に戦略を学んでおけば、その後インプットで不動産登記法や商業登記法を学んだときに、「あ、これは記述でこう使うんだ」とつながっていく。そうすると知識がただの暗記で終わらず、“使える形”で身についていきます。
つまり、「知識」→「戦略」ではなく、「戦略」→「知識」の順でも十分アリなんだと実感しました。
これからの方針
もちろん、不安がゼロになったわけではありません。不動産登記法や商業登記法のインプットをしっかり積まないと、記述で合格点を取れるわけがないのは分かっています。
でも、今は先生の言葉を信じて、流れに乗っていくことにしました。通信講座のペースメーカーは、やはり講師陣。自分でコントロールできる部分と、あえて流されてみる部分。そのバランスを取りながら進めていくのが、一番の近道なのかもしれません。
これからも、記述の講座を“怖がらずに”取り入れていこうと思います。
最後に
司法書士試験の勉強は、本当に長い旅です。ときには「まだ早いんじゃないか」と不安になり、ときには「このまま進んでいいのか」と迷うこともある。
でも大事なのは、立ち止まってしまわないこと。講座が配信されたのなら、それには必ず意味がある。信じてついていくこと。
僕もまだまだ道半ばですが、こうしてブログに書くことで自分の気持ちを整理しつつ、また次の一歩を踏み出していこうと思います。
今日もまた、Vマジックと共に机に向かいます。
👉 司法書士受験生のみなさん、もし同じように「まだ知識が足りないのに記述が始まってしまった!」と焦っている方がいたら、一緒に頑張っていきましょう。


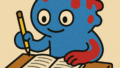
コメント