司法書士試験の勉強をしていると、ついつい「問題が解ければよし」となりがちです。テキストは分厚く、講義動画も膨大。復習の時間も限られている以上、効率を求めて「問題集中心」の学習に偏ってしまうのは自然な流れです。
しかし、それでは知識の網羅性に欠け、本試験での「初見問題」への対応力を失いかねません。
そこで今回は、私自身の勉強法の反省を踏まえつつ、司法書士試験における「正しいインプット法」について整理してみます。特に以下の3点を軸に解説します。
- テキストと問題の関係性を正しく捉える
- 埋め込まれた問題や例題を拾い上げる
- 表やまとめの暗記を別枠で行う
1. テキストと問題は「主従関係」ではなく「両輪」
まず強調したいのは、テキストと問題は主従関係ではないということです。問題はあくまで「確認の手段」であり、テキストは「体系を作るための本体」です。
多くの受験生が、問題演習に偏る理由はこうです。
- 問題を解く → 正解できた → 理解できた気になる
- テキストを読む → 長くて覚えづらい → 「効率が悪い」と感じる
しかし司法書士試験では、過去問知識をそのまま出す設問は半分以下。残りは「条文や制度の理解」や「表の知識」から応用的に問われます。つまり、テキストの読み込みなしでは必ず穴が生まれるのです。
したがって、勉強の流れを「テキストを読む → 講義を聞く → 問題を解く」で終わらせるのではなく、「問題を解いた後に再びテキストへ戻る」ことが重要です。この「テキストへの還流」を繰り返すことで、体系の理解が深まります。
2. テキストに埋め込まれた「隠れ問題」を拾う
司法書士試験用のテキストは、ただの解説書ではありません。実は随所に「隠れ問題」が散りばめられています。例えば、
- 本文中に自然に挿入された過去問の肢
- 例題・図解の中でさらっと聞かれている知識
- コラム的に紹介される「よくある出題パターン」
これらは独立した問題集には出てこないものの、本試験で狙われる「周辺知識」です。ここをスルーすると、インプットが偏り「問題に出たことしか知らない」という危険な学習状態に陥ります。
実践的な方法としては、
- テキストを読む際に「問題形式で書かれている部分」にチェックを入れる
- そこだけを別ノートに抜き出すか、付箋でマーキングする
- 復習時には「問題集+テキスト内の隠れ問題」を必ず一緒に確認する
こうしておけば、テキストを「問題集化」でき、演習の幅が広がります。
3. 「表やまとめ」は別枠で覚える
司法書士試験のテキストには、多くの「表」や「比較図」が出てきます。例えば、
- 債権各論の債務不履行と不法行為の比較
- 不動産登記法の添付情報一覧
- 商業登記法の役員変更登記の要件表
これらはそのまま試験に直結しますが、問題演習では一部しか問われません。問題だけを解いていると、表の全体像を覚えきれず「部分知識の寄せ集め」で終わってしまうのです。
そこで、表や一覧は「暗記対象」として独立させる必要があります。具体的には、
- 表を自分の手で書き直す(アウトプット型暗記)
- A4用紙や暗記カードに縮小版をまとめて持ち歩く
- 毎日のスキマ時間に「表だけを確認する時間」を設ける
こうすれば、問題演習と表暗記が車の両輪として機能し、知識の偏りを防げます。
4. 復習は「問題中心+表確認」の二段構え
日々の復習では、どうしても「問題だけ」を回しがちです。しかし、そこで表やテキストへの立ち戻りを怠ると、体系が崩れます。復習時の工夫としては、
- 1周目:問題を解く → 間違えた箇所をテキストで確認
- 2周目以降:問題を解く → 表やまとめを暗記で確認
という「二段構え」で進めるのが理想です。つまり「問題は知識確認」「表は知識の底上げ」と役割を分けて復習に組み込むのです。
5. 「やったつもり学習」からの脱却
司法書士試験は、範囲が膨大であるがゆえに「やったつもり学習」に陥りやすい試験です。問題を解いて○がつけば「理解できた気」になり、表を読み飛ばせば「そこまで大事じゃない」と思い込みます。しかし実際の本試験は、その「隙間」をついてきます。
だからこそ、
- 問題に出ない知識もテキストから吸収する
- 表やまとめは「暗記リスト」として独立管理する
- 問題を解いた後には必ずテキストに戻る
この3つを徹底することが、真の意味での「正しいインプット」です。
まとめ
司法書士試験の学習は、どうしても「アウトプット重視」に偏りがちです。しかし、本試験を突破するには、問題演習で出てくる知識+テキストで拾える周辺知識+表の丸暗記の三位一体が不可欠です。
- 問題は解いて終わりではなく、必ずテキストに還流する
- テキスト内の「隠れ問題」を拾って独自に演習化する
- 表やまとめは別枠で暗記対象として繰り返す
このサイクルを回せるかどうかで、合否は大きく分かれます。
司法書士試験は、知識の量だけでなく「網羅性」と「体系性」が問われる試験です。効率を追うあまり「偏ったインプット」に陥らないよう、ぜひこの3つのポイントを意識して学習を進めてみてください。
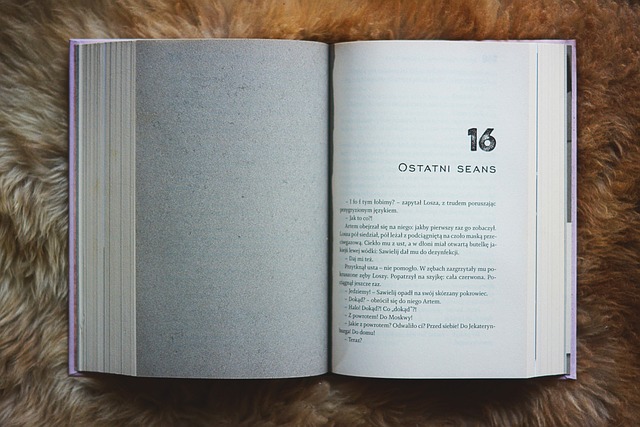


コメント