司法書士試験の勉強は、覚える量が膨大です。
民法・不動産登記法・商業登記法・会社法・民訴…と科目が多く、しかも条文・判例・手続きの細部まで暗記が必要。
いくら集中して勉強しても、時間が経つと「あれ、どこで見た論点だっけ?」と忘れてしまうこともしばしば。
そんな中で私が注目したのが、精神科医・樺沢紫苑さんが紹介している「2週間に3回、記憶を取り出す」**という記憶術です。
これは単なる復習の話ではなく、脳の記憶システムに沿った合理的な学習法。
司法書士試験のような長期戦の学習に、非常に相性がいいと感じました。
樺沢紫苑流・記憶術のポイント
樺沢さんによると、私たちが新しいことを覚えるとき、情報はまず海馬に短期記憶として保存されます。
しかし海馬はあくまで一時的な保管庫。数日〜数週間で忘れてしまう性質があります。
そこで重要なのが「記憶の取り出し(想起)」です。
学んだ情報を繰り返し思い出すことで、記憶は側頭葉に移され、長期記憶として定着します。
その“最小限の条件”が、2週間の間に3回、取り出すことだというのです。
ポイントは、「読み返す」ではなく思い出すこと。
つまり、テキストを見ながら確認するのではなく、問題を解いたり口で説明したりして、頭の中から情報を引き出す行為が必要です。
司法書士試験にどう応用できるか?
この理論を司法書士の学習に応用すると、「学んだ内容を2週間の間に最低3回思い出す」というサイクルが基本になります。
つまり、インプットした後、1回目はすぐに、2回目は数日後、3回目は2週間以内に行う。
たとえば、民法の担保物権を8月25日に学んだ場合:
- 1回目(即日)
当日中に問題演習や口頭で説明しながら復習。 - 2回目(数日後)
8月28〜30日あたりに同じ範囲の問題を再度解く。 - 3回目(2週間以内)
9月7〜9日までにもう一度、思い出しを行う。
この3回をクリアすれば、海馬にある短期記憶が側頭葉の長期記憶に移行し、忘れにくくなるというわけです。
「見る」より「取り出す」 ― 想起練習の重要性
司法書士試験では、「覚えたつもり」が一番危険です。
テキストを読んで「分かった気」になっても、実際に問題に直面すると全く出てこないことがあります。
これは、記憶の“入力”だけで“出力”の練習が不足している証拠。
樺沢さんの理論が重視するのは、この「出力=想起」です。
つまり、学習の段階から「自分の頭から引き出す」練習を組み込むことが重要。
具体的には:
- 過去問を解く
- 条文番号を言い当てる
- 他人に説明する
- 白紙に図や表を書き出す
これらはすべて「記憶の取り出し」に該当します。
実践スケジュール例
司法書士試験の学習で、2週間3回ルールを回すためのスケジュール例です。
例:民法の1ユニット(8月25日開始)
- Day 0(8/25):インプット(テキスト+講義)→ すぐに問題演習(1回目の想起)
- Day 3(8/28):該当範囲の問題再演習+条文口頭確認(2回目の想起)
- Day 12(9/6):週次復習の中で再度問題演習(3回目の想起)
このように、インプット日を起点に2週間の中で3回の“取り出し”を計画的に組み込むのがポイントです。
長期戦における大きなメリット
司法書士試験は1年スパンの勉強が普通です。
多くの受験生は、春にやった科目を夏には半分以上忘れてしまいます。
これは「2週間以内の3回取り出し」が不足しているから。
この方法を使えば、復習のタイミングが明確になり、漫然と見返す無駄が減るという大きなメリットがあります。
さらに、記憶の土台が早い段階で固まるため、直前期は細かい論点確認や演習に時間を割けます。
注意点
- 1回目をサボらないこと:学習直後の想起が最も重要。
- “見るだけ復習”は禁止:必ず頭から引き出す形で行う。
- 手間はかかる:最初は復習量が増えたように感じるが、長期的には効率が上がる。
まとめ
樺沢紫苑さんの「2週間に3回、記憶を取り出す」というシンプルな理論は、司法書士試験のような長期・大量暗記型試験と非常に相性が良いです。
勉強の流れを「覚える→思い出す→また思い出す→さらに思い出す」という形に変えるだけで、記憶の残り方が劇的に変わります。
そして、この“思い出す”タイミングを2週間の中で3回組み込むことが、忘れない知識を作る近道です。
あなたの学習計画にも、ぜひこの「2週間3回想起ルール」を組み込んでみてください。
きっと、半年後の記憶の残り具合が変わっているはずです。
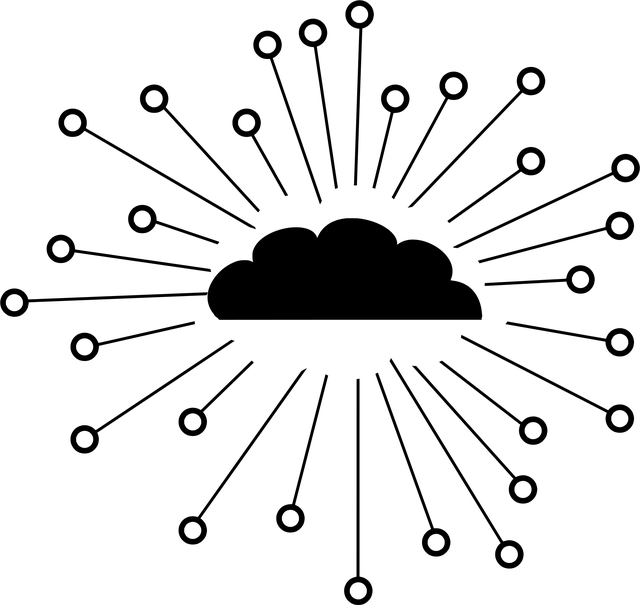
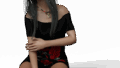

コメント