世の中には「両利きの経営」という考え方があるようです。

いままでどおりのことを深堀するのと、あたらしい挑戦にトライするのと、2つの部署を会社に置くということ。
NECなんかそれで成功しているとか。
でも、これは実に日本的で、実際、スタンフォードの授業で扱う具体例は日本の会社くらいしか出てこない。
失敗したくない日本の社長にとって都合のいい考え方とのこと。

別に批判しているのではなく、使い方を間違っているのだと。
で、司法書士の、まさに僕がやっている受験勉強と、合格後の活動を考えたとき・・・
若いころに合格すれば、普通にキャリアアップして、儲ければいいけど。
もう相当年ですからね。僕は。
全然違うIT関連で長くやってきたから、そんな僕がとなると、もちろん受験勉強や合格後の仕事の深堀はあるけれど、それ以外の価値の創出(僕なりの)は必要になる。
ということで、受験勉強中であっても、つねにアンテナを張って、という「両利きの受験勉強」こそが、モチベーション維持においても、実際合格後のビジョンにおいても重要と思えてきた。
経済学者のシュンペーターは、経営はビジョンとツールだというらしい。
今日の日経でも言ってた。

なんか、悲観バイアスをなくそーというウリケ・シューデさんが、「シン・日本の経営」って本をだしているらしいし、しっかりビジョンとツールでやれば、全然今の日本もOKなんでしょ。
司法書士って、海外に打って出る職業じゃないから、今の日本、これからの日本がどうなるかにものすごく影響する職業だと思う。
僕らしい司法書士のビジョンは今のうちに作っておかないと。
受験勉強のためのツールだけでなく、新しい展開へ向けた価値の創出が必要。
というのも、司法書士って、もうある種、コモディティ化しているというか、不動産売買や相続や会社立ち上げの登記って感じでしょ。
でももっと、世の人たちに、どんなことを司法書士にそうだんできるかとか、司法書士側からもアピールが必要なはず。
たとえば、人は成人し、就職し、結婚する。子供ができる頃に、あるいは中堅どころの身分になったころに、住宅ローンで家を買う。
で、子供が巣立って、その家を子供に渡すのか。
またつれあいもいなくなって一人になったら、どこかサポートの手厚い高齢者住宅に移るのか。
だったら前の家はどうする?とか。
そういうこと考えると、人生のいろんなタイミングで、司法書士が手伝えることがあるはず。
IT的にいえば、いくつかの質問に答えるだけで、今後自分にとって必要なこと、司法書士からアドバイスできることが時系列的に出てくるとか。
いうならば、占いの鑑定結果のようなもので。
あなたはこんなタイプだから、5年後、10年後はこうこう、と、転ばぬ先の杖、というサポートもあるはず。
そうこうしているうちに、世の中は、団塊世代の最後の年齢が75歳になろうとしている、とかなると、今の世の中の流れ、政治の流れ、法律改正の流れに合わせて、いろんなことが話せるはず。
そういうアンテナは常に張ってないと。
ということで、私は両利きでいこうとおもいます。
今日は頭結構使ったかな。
あ、そういえば、今日って、「とんちの日」らしいですよ。
って、なんだそれ、一休さんか、と、車のナビの「今日は何の日」の声に反応したが。
あ、そっか、だから1月9日はいっきゅーで一休さんかと、妙に納得した。
受験勉強しているから、頭が常に活性化して、さえてるんかなぁ。あんまり関係ないか。
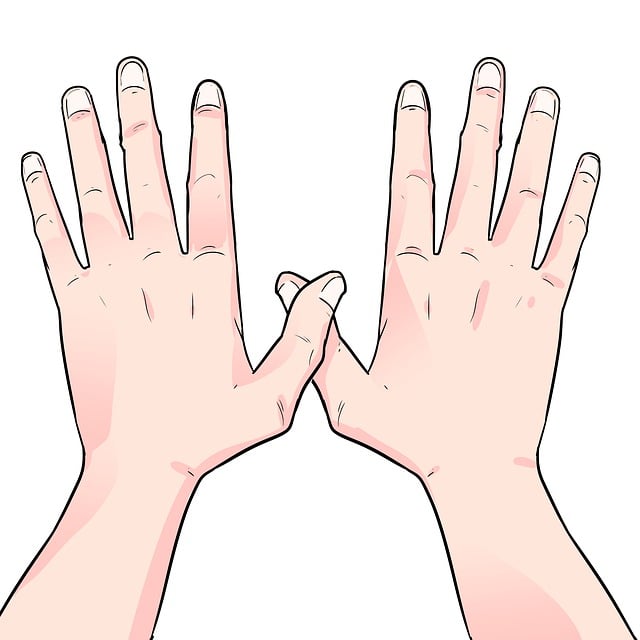


コメント